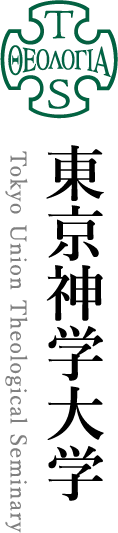- 2025.08.28
- トピックス
学長室から――神学校と召命
前回、H・リチャード・ニーバーによりながら、教会の牧師の務めに召される召命の四つの要素について見ました。一つは、最も基本的な、キリスト者になるようにとの召命です。その次に、内密の、あるいは、内心の召命と呼ばれるもの、つまり、「召命感」があります。さらに、第三の要素をニーバーは「providential」な召命と呼んでいます。神様によって備えが与えられることを指しています。そして、最後に「教会的召命」があります。教会によって召し出され、招かれることを言います。これら四つの全ての要素が整ってこそ召命があると言えるということになるのです。――それでは、そこに神学校は、どのようにかかわるのでしょうか。
神学校としての東京神学大学では、上記の第一と第二の召命を前提として、第三と第四の召命が特に問われると言えるでしょう。第四の要素について先に述べるなら、受験時に教会からの推薦を受けるということが、ここに含まれます。しかし、それだけではありません。日本基督教団とのかかわりで言えば、その教師になるためには、神学校を卒業してから教師検定試験を受けることになります。これもまた召命の第四の要素にかかわっています。さらにまた、教師検定試験だけでなく、神学校での教育が、教団の「教憲」第9条に「本教団の教師は、神に召され正規の手続きを経て献身した者とする」とある、その「正規の手続き」の一部であると考えれば、東京神学大学で「教会的召命」が問われ、吟味されることになるのは明らかでしょう。
それと同時に、神学校においては、第三の要素における召命が問われます。必要な賜物が備えられるようになること、神学校という環境によって、神様が導かれることが問題です。こうして見ると、神学校において、召命は自明の、疑い得ない事柄ではなく、むしろ、絶えず、繰り返し吟味される事柄であるということがわかります。神学校に身を置くというのは、そういう召命の吟味を重ねる歩みをしていくことなのです。(神代)