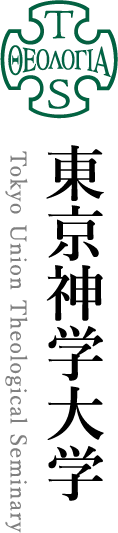- 2025.08.20
- トピックス
学長室から――召命の四つの要素
H・リチャード・ニーバーという20世紀に活躍したアメリカの神学者がいますが、あるところでニーバーは、教会の牧師の務めに召される召命について、四つの要素があると述べています。一つはキリスト者になるようにとの召命です。およそ、キリスト者であるならば、誰でも神様に、イエス・キリストに、そして、教会に仕える者であるからです。
そして、その次に、内密の、あるいは、内心の召命と呼ばれるものがあるとニーバーは言います。これは、いわゆる「召命感」です。教会の牧師の務め(もちろん、これとの深いかかわりの中での、キリスト教学校の聖書科教師の務めも考えられますが)になるようにと神様から召されている、招かれているという思いのことです。
第三の要素をニーバーは「providential」な召命と呼んでいます。普通なら「摂理的」と訳したい言葉ですが、この場合は、もう少し意味が広いようです。というのも、召命のこの要素についてニーバーは「職務を遂行するのに必要な賜物が、ある人に備えられること、および、あらゆる環境によって、その人を神が導くこととを通して、〔牧師の務め〕の業を引き受けるようにとの招きと命令」だと言っているからです。「あらゆる環境によって、その人を神が導くこと」は「摂理」と呼んでもよいでしょうが、「職務を遂行するのに必要な賜物がある人に備えられること」まで「摂理」と呼ぶのは少々わかりにくいでしょう。ですから、「providential」は「神によって備えが与えられていること」とでも訳したらよいかと思います。
そして、最後に「教会的召命」があります。教会によって召し出され、招かれることを言います。これら四つの全ての要素が整ってこそ召命があると言えるということになるのです。――それでは、そこに神学校は、どのようにかかわるのでしょうか。それについては次回に書いてみます。(神代)